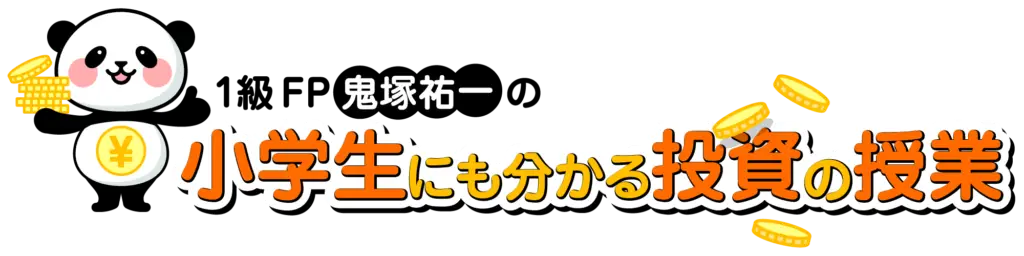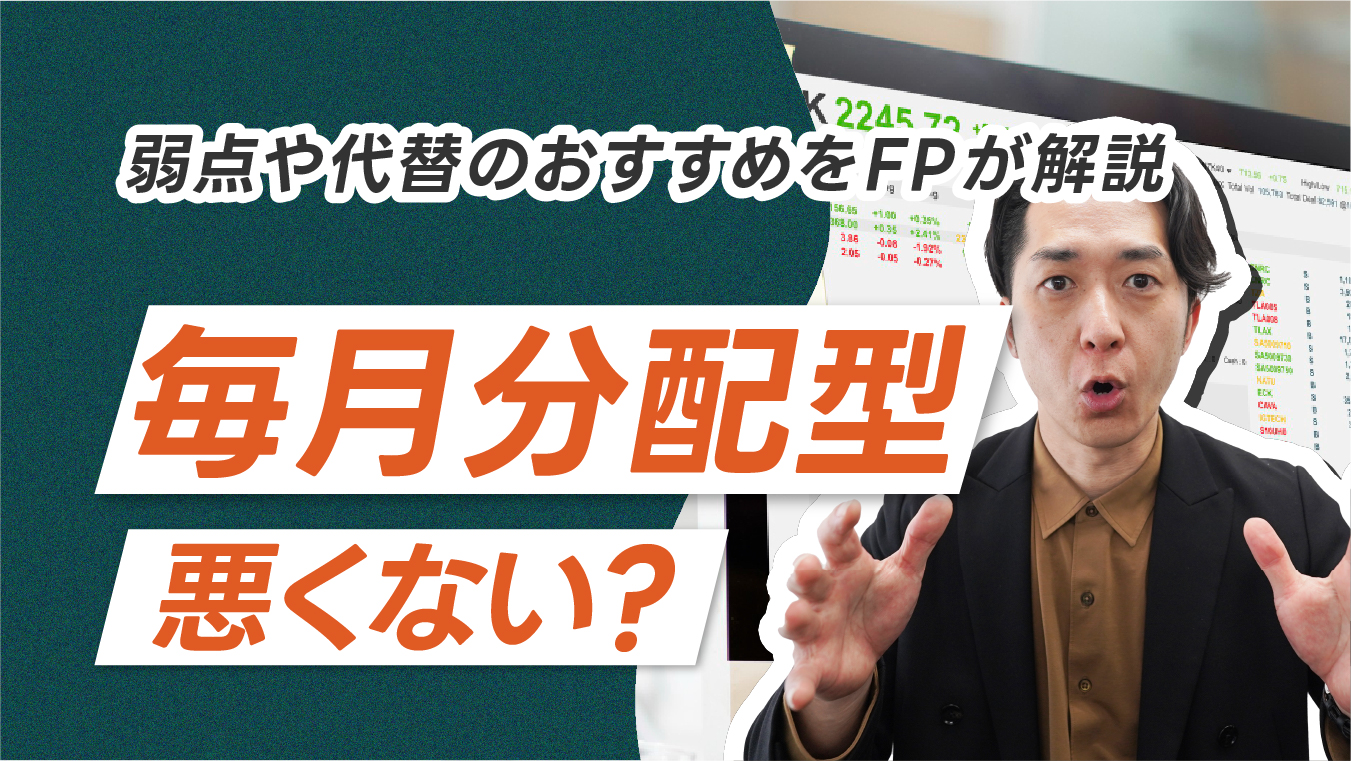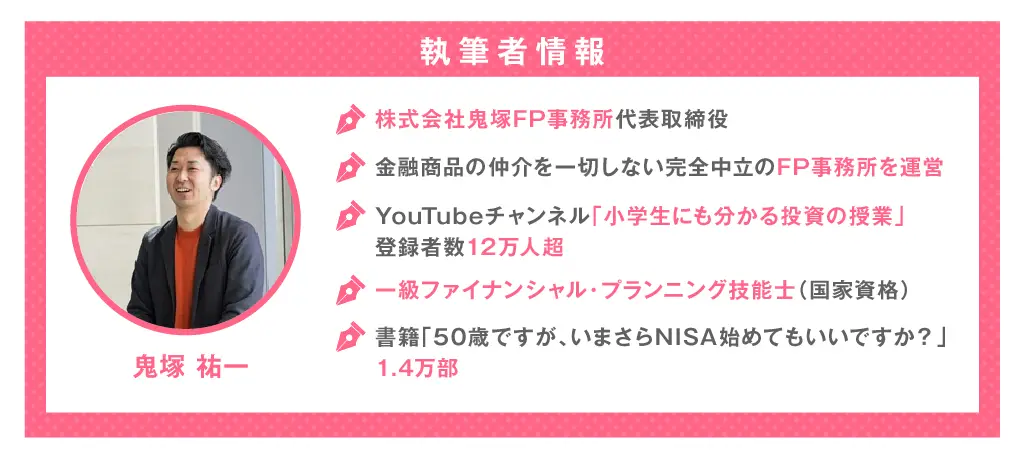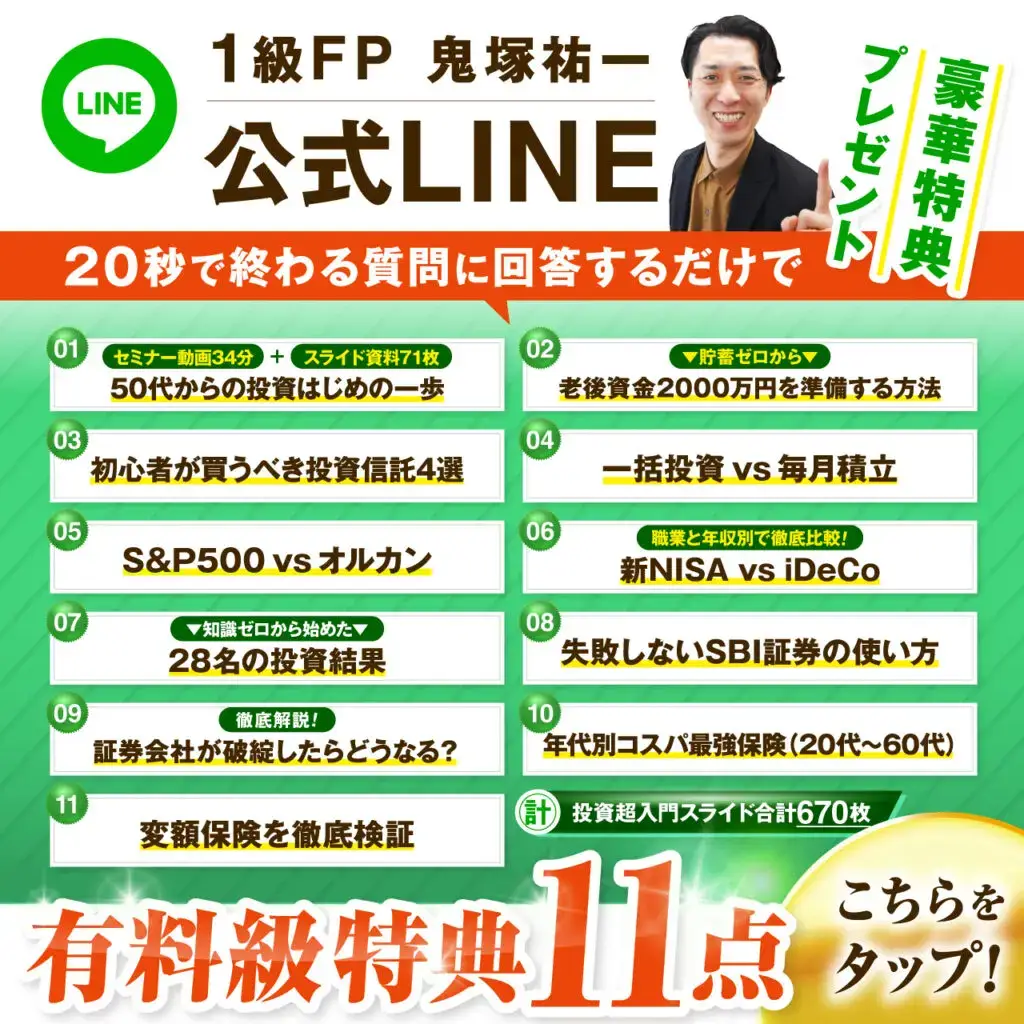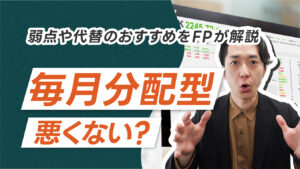「毎月分配型の投資信託って悪いものなの?」
「安定した収入源として魅力があるけど、デメリットも知りたい!」
「NISAで毎月分配型に投資できるの?」
このような疑問をお持ちではありませんか?
毎月分配型の投資信託は、定期的な現金収入が得られる点が魅力ですが、複利効果が得にくいなどの弱点も存在します。そこで本記事では、1級FP技能士である私鬼塚が以下のテーマについて解説します。
- 毎月分配型投資信託の特徴
- 毎月分配型投資信託の人気ランキング
- 毎月分配型投資信託のメリット・デメリット
ぜひ参考にしてみてください。
なお、私鬼塚のLINEに登録していただくと、「S&P500 VS 全世界株式徹底解説」「投資初心者が買うべき投資信託4選」などの特典を受け取れます。資産形成に悩んでいる方はぜひ登録してみてくださいね!
毎月分配型の投資信託は悪くない?概要をサクッと解説

毎月分配型の投資信託について理解するには、基本的な特徴や費用・分配金の仕組みを押さえることが重要です。ここでは重要なポイントを3つ紹介します。
- 毎月分配型の概要
- 費用の目安
- 分配金の目安
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 毎月分配型の概要
毎月分配型の投資信託とは、毎月決算を行い、収益の一部を分配金として投資家に毎月支払う仕組みの投資信託です。
運用成果をこまめに現金で受け取りたいというニーズに応えて設計されているため、とくに老後の生活費や年金の補助として利用されることが多いでしょう。
ただし、分配金を受け取ることで手元の現金は増えるものの、その分運用資産が減少するため、無分配型の投資信託と比較して資産の成長が遅くなる傾向にあります。

つまり、毎月分配型は定期的な収入を重視する人には便利ですが、長期的な資産形成を目指す場合は運用効率が下がるおそれがあるということです。
2. 費用の目安
毎月分配型の投資信託を利用する際にかかる費用は、主に購入時手数料・信託報酬そして換金時の手数料や信託財産留保額があります。
各費用の詳細は、以下のとおりです。
| 購入時手数料 | 投資信託を購入するときにかかる費用 |
| 信託報酬 | 運用や管理のために毎日自動で差し引かれる費用 |
| 信託財産留保額 | 解約時にファンドの資産に残すため差し引かれる費用 |
購入時手数料は、最大で投資額の3.3%ほどかかる場合があります。
ただし、SBI証券や楽天証券を利用すれば、購入時手数料はかかりません。
信託報酬は、年率1%台半ばから2%台前半の商品が一般的です。また、換金時に最大0.5%程度の手数料や留保額が必要な場合もあります。
以上の費用は、ファンドや販売会社によって異なるため、購入前に交付目論見書で必ず確認しましょう。
3. 分配金の目安
毎月分配型投資信託の分配金は、運用益の一部が毎月現金で支払われる仕組みですが、その金額はファンドごとに異なります。
分配金の目安を知りたい場合は、過去の分配実績や年間分配金利回りを参考にするとよいでしょう。
たとえば、年間分配金利回りが6%のファンドに100万円投資した場合、年間で約6万円、月あたり約5,000円の分配金が受け取れる計算となります。



ただし、これはあくまで過去の実績に基づく目安であり、今後も同じ水準が続くとは限りません。
また、分配金が支払われるとその分だけ基準価額が下がるため、分配金だけでなく基準価額の変動も合わせて資産全体の増減を確認することが重要です。
分配金には税金もかかるため、実際の手取り額はやや少なくなる点も押さえておきましょう。
毎月分配型の投資信託のランキングを紹介


毎月分配型の投資信託は、分配金を毎月受け取れることから一定の需要があります。
楽天証券における最新の毎月分配型投資信託ランキングは、以下のとおりです。
| 順位 | 投資信託 | 管理費用(含む信託報酬) | 直近1年間の分配金総額 |
|---|---|---|---|
| 1位 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 1.903% | 1,800円 |
| 2位 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 1.727% | 2,700円 |
| 3位 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 1.54% | 420円 |
| 4位 | フィデリティ・米国株式ファンド Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし) | 1.65% | 3,500円 |
| 5位 | グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型) | 1.903%※IFA 手数料あり | 950円 |
以上のファンドは、高い分配金利回りや安定した運用実績が評価されています。なお、楽天証券で投資信託を購入する場合、基本的に購入時手数料はかかりません。
なお、楽天証券やSBI証券におけるおすすめ投資信託については、以下の記事で解説しています。
ぜひ参考にしてみてください。
毎月分配型は悪くないは本当?メリットを解説


毎月分配型の投資信託には多くのメリットがあります。ここでは、投資家にとって重要な3つのメリットについて詳しく紹介します。
- 定期的な収入源になる
- 運用している実感がある
- 資産を取り崩しながら運用できる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 定期的な収入源になる
毎月分配型の投資信託の最大のメリットは、定期的に現金収入が得られる点です。
とくに、退職金や老後資金などまとまったお金を運用しながら、生活費や趣味の費用に毎月充てたい人には向いている商品です。
投資信託を解約せずに運用成果を毎月こまめに受け取れるため、資産運用の実感も得やすいでしょう。
分配金の金額や支払いは運用状況によって変動しますが、毎月お金が入る安心感はほかの投資信託にはない魅力といえます。
2. 運用している実感がある
毎月分配型の投資信託は、分配金が毎月振り込まれるため、自分が資産運用をしているという実感を持ちやすいのが大きな特徴です。
投資の経験が浅い人や資産運用にあまり興味がない人にとっては、分配金が定期的に入ることで「お金が増えている」「運用している意味がある」と感じやすいでしょう。
分配金を受け取るたびに、資産運用の成果を目に見える形で確認できるため、投資を継続するモチベーションにもつながります。



分配金が入ることで生活のなかで資産運用の存在を意識しやすくなり、安心感や楽しさを感じられます。
3. 資産を取り崩しながら運用できる
毎月分配型の投資信託は、資産を運用しながら計画的に取り崩していきたい人に向いている商品です。
毎月分配型の投資信託を運用しつつ分配金を受け取ることで、資産寿命を延ばしながら定期的な現金収入を確保できるのが大きなメリットです。
この仕組みは、リタイア後の生活資金の補填や資産を長期間かけて少しずつ使いたいというニーズにマッチしています。
ただし、相場が悪いと元本の減少が早くなる恐れもあります。
そのため、資産全体の動きや分配金の仕組みを理解し、自分のライフプランに合った使い方を考えることが大切です。
毎月分配型は悪くないと思っている人が見落としているデメリット


効果的な資産運用のためには、毎月分配型投資信託のデメリットもしっかり理解する必要があります。ここでは見落としがちな3つの重要なデメリットを紹介します。
- 複利効果が得にくい
- 元本が減少するリスクがある
- 毎月分配型は新NISA対象外
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 複利効果が得にくい
毎月分配型の投資信託における最大のデメリットは、複利効果を十分に活かせない点です。
複利は、長期投資で資産を大きく増やすための重要な力です。
しかし、毎月分配型では利益が分配金として手元に戻ってしまうため、その分運用資産が減り、複利の恩恵を受けにくくなります。
取り崩し額が大きくなるほど、複利効果による資産の成長が抑えられます。
そのため、毎月分配型は目先の収入を重視する人には便利ですが、資産を大きく増やしたい人には不利な仕組みだといえるでしょう。
2. 元本が減少するリスクがある
毎月分配型の投資信託は、毎月分配金がもらえる点が魅力ですが、その分配金の原資に注意しなくてはいけません。
運用で得た利益だけで分配金をまかなえない場合、元本の一部を取り崩して分配金として支払うことになります。



つまり、見かけ上は毎月お金がもらえていても、実際には自分が投資したお金が少しずつ戻ってきているだけという状況もあり得ます。
このように元本を取り崩す分配が続くと、投資信託の資産そのものが減り、将来的な運用成果や分配金の維持が難しくなるリスクが高くなるでしょう。
とくに、高い分配金をうたうファンドほど、元本を削って分配金を出している場合が多く、長期的な資産形成には不向きだといえます。
毎月分配型は、安定収入を求める人には便利ですが、元本減少のリスクをしっかり理解して選ぶ必要があるでしょう。
3. 毎月分配型は新NISA対象外
毎月分配型の投資信託は、2024年から始まった新NISA制度では対象外です。
新NISAは長期的な資産形成を目的として設計されており、毎月分配型のように定期的に分配金を支払う商品は、効率的な資産の積み上げに向かないと判断されたためです。
分配金には通常20%ほどの税金がかかるため、課税口座で運用する場合は手取りが減ってしまいます。
今後、高齢者向けNISAで毎月分配型が対象に加わる可能性も議論されていますが、現時点では新NISAの非課税枠を活用したい人にとっては大きなデメリットとなります。
新NISAについては、以下の記事で詳しく解説しているのでぜひ参考にしてみてください。


毎月分配型より優秀?自動定額売却サービスの特徴


毎月分配型の代替として、自動定額売却サービスという選択肢があります。このサービスには3つの大きなメリットがあります。
- 毎月の受取額を自由に設定できる
- 資産全体の寿命を延ばせる
- 手間がかからない
それぞれ詳しく説明します。
なお、SBI証券や楽天証券では1,000円以上から1円単位で売却額を設定できます。
1. 毎月の受取額を自由に設定できる
自動定額売却サービスは、保有している投資信託を毎月自動的に売却し、現金を受け取る仕組みです。
自動定額売却を設定すれば、毎月受け取る金額を自分で自由に設定できます。



好きな金額を指定できるため、生活費や趣味など必要に応じて受取額を調整できるのが大きな魅力です。
一方、毎月分配型の投資信託は分配金の額が運用状況やファンドの方針で決まるため、投資家が金額をコントロールできません。
自動定額売却サービスなら、受け取りたい金額やタイミングを自分で決められるので、資産の取り崩しを計画的に行いたい人にとって非常に使いやすいでしょう。
2. 資産全体の寿命を延ばせる
自動定額売却サービスは、毎月分配型投資信託と異なり、資産を計画的かつ効率的に取り崩せるのが大きな特徴です。
たとえば、相場が好調な時は売却額を抑えて資産の減少を防いだり、必要なときだけ受取額を増やしたりすることも可能です。
相場状況に応じて取り崩しペースを調整することで、資産寿命を延ばせます。
また、低コストのファンドを選んで運用しながら必要な分だけ取り崩せるので、毎月分配型よりも複利効果を活かしやすいのもメリットです。
自動定額売却サービスを利用して計画的な取り崩し設定を行えば、毎月分配型より資産寿命を延ばせるでしょう。
3. 手間がかからない
自動定額売却サービスは、一度設定してしまえば、毎月自動的に投資信託を売却して現金を受け取れるので、手間がほとんどかからないのが大きな魅力です。
売却金額や受取日・売却方法(金額指定・定率指定・期間指定など)を最初に決めておけば、あとは自動で手続きが進むため、売却の操作をする必要がありません。



また、設定内容の変更や停止もネット上でかんたんにできるので、生活スタイルや資金計画が変わったときも柔軟に対応できます。
忙しい人や投資にあまり手間をかけたくない人にとって、とても使いやすい仕組みといえるでしょう。
毎月分配型だけでなく定期売却サービスも選択肢に入れておこう!


毎月分配型投資信託には定期的な収入が得られるメリットがあるものの、複利効果が得にくく元本が減少するリスクもあります。そこで、自動定額売却サービスも検討してみましょう。
自動定額売却サービスなら受取額を自由に設定でき、資産寿命も延ばせます。さらに、一度設定すれば自動的に処理されるため手間もかかりません。
自分の投資目的や生活スタイルに合わせて、両方のメリット・デメリットを比較し、最適な選択をしていくことが大切です。
なお、私鬼塚のLINEに登録していただくと、「S&P500 VS 全世界株式徹底解説」「投資初心者が買うべき投資信託4選」などの特典を受け取れます。



資産形成に悩んでいる方はぜひ登録してみてくださいね!